組織風土研究会報告書
「組織風土を従業員はどうとらえているのか?
~個人の認識とその影響~」
「組織風土研究会」とは
組織風土研究会は、企業や組織運営における課題解決の基盤となる「組織風土」に焦点を当て、働く人の視点からその実態について明らかにするとともに、個人の認識や行動といった多様な観点から検討することを目的としています。
「組織風土」は個人の属性や価値観、考え方などによってとらえかた方が異なるため、共通認識を形成することが難しいテーマです。
そこで本研究会では、さまざまな業種・職種で働く5,000人を対象に、自身の職場をどう感じているかや、働くうえで大事にしている価値観などについてのアンケート調査を実施しました。
調査では、「組織風土」に対する日常的な意識の状況や理想とする「組織風土」のほか、職場に対して希望を抱いているかやワーク・エンゲイジメント、ストレスといった個人の反応との関係を統計的に分析することで、その影響を多面的に検討しています。
本研究を通じて、 「組織風土」に対する共通認識の形成や議論を行う際の重要な視点が明らかになりました。その内容を報告書としてまとめました。組織を運営する立場の人のみならず、一般に働く人にとっても、職場との向き合い方について考える一助となれば幸いです。
調査結果のサマリー
研究会における主な分析結果は次のとおり。
1. 組織風土の多次元構造 (報告書 第1章)
・組織風土は経営理念、人間関係、上司や経営陣の行動といった多様な要素の影響を受ける。「企業全体(マクロ)」や「職場単位(メゾ)」という多次元的な観点でとらえることが重要である。
・組織風土は客観的な評価の際には重視されにくいものの、日常的には身近に意識されやすい要素である。
・健康関連KPIとの関係では、「協力的でチームワークを重視する組織」や普段から組織風土を意識する姿勢が良好な結果につながる傾向がみられる。
2. 理想と現実のギャップ : 価値観と状況認識のズレ (報告書 第2章)
・「風通しが良くフラットな組織」が、性・年代・働くうえで重視している価値観に関係なく、高い割合で支持されている。
・一方、実際の職場の組織風土に対する認識には差があり、現実とのギャップが存在する。
・残業や会議の無駄、人事評価制度への不満、評価に関する課題が職場改善の声に影響している。
3.個人と組織との距離感と対応スタイルの分岐 (報告書 第3章)
・①「何か自分が発言したり行動を起こしても、職場が変わることは難しいと感じている」という設問に対して、「どちらかというとそうだ/どちらかというとそうではない」という中間的な回答をした層は、理念・やりがい・同僚への好意的な感情を持つ傾向がある。
・②「職場の慣習について自分の意にそぐわないことがあっても、わざわざ意見表明しない」という設問に対して、「そうだ/どちらかというとそうだ」と回答する層は、上司や同僚への好意的感情を維持していることが多く、日常的な信頼・相談関係がその背景にあるとみられる。
・ただし、②で明確に「そうだ」と答えた層には強いストレスを感じる人が多く、職場の慣習に対して意見表明しないと明確に認識していることは、ストレスにつながる可能性がある。
研究会委員
本研究会の立ち上げにあたり、神戸大学経済経営研究所准教授 江夏 幾多郎氏 を委員に迎えました。
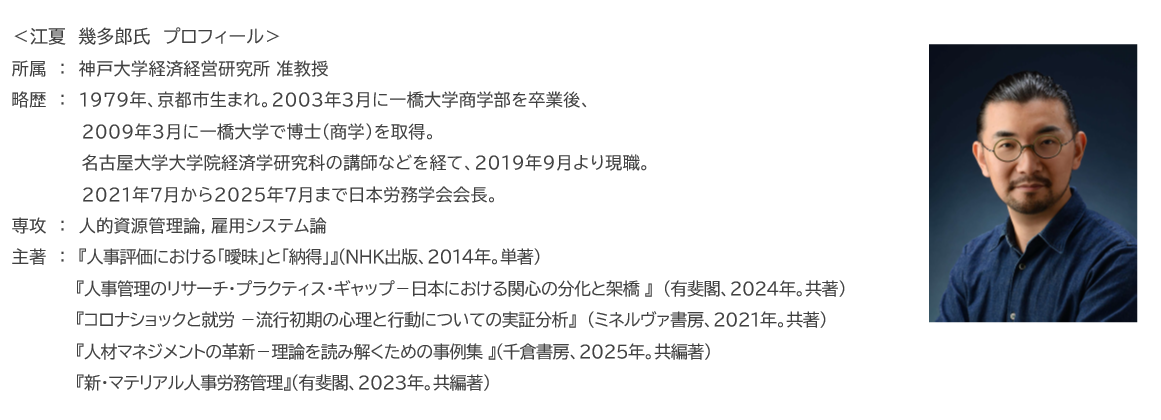
< 江夏氏 コメント>
・「風通しが良くフラットな組織」「協力的でチームワークを重視する組織」が従業員の健康についてプラスで、「競争的な組織」「ヒエラルキーが厳格な組織」がマイナスということが示されたことの価値は高い。前者のタイプが実際には多く、後者のタイプが少なめというのは、日本の職場は巷間で言われているほどには悪くない、ということかもしれない。しかし、とりわけ「風通しが良くフラットな組織」については、「そういうところで働きたいけれども実際には働けていない」という従業員が、全サンプルの25%程度はいることが推定され、課題も見出される。
・また、そういう組織においても、自分の発言・行動が職場の変化に結びにくい、意にそぐわない慣習について意見表明しない、と感じる従業員が多い(他の風土と比較して、顕著に少ないわけではない)。また、職場をより良くするために何かをしたことがある従業員が少ないこと、彼らの健康や職務態度が良好であることもうかがえた。これらの事柄は、多くの従業員において、職場の風通しの良さやフラットさを強く望むにもかかわらず、自らの貢献によって維持したり、高めたりする意識が、必ずしも強くないことが推定される。
・「権限委譲型で自律的に働く組織」「挑戦とイノベーションを重視する組織」は、経営学的にいうと、創造性との親和性がとりわけ高いが、「風通しが良くフラットな組織」「協力的でチームワークを重視する組織」と比べて従業員の健康への寄与は少し劣るがそれほど悪いものではなく、希望や幸福感については遜色ない。労使双方のニーズを充足させる「落とし所」になりうる。
・全体的にそうだが、「風通しが良くフラットな組織」においてすら、業務や会議における無駄、人事評価制度への強い不満が見出されている。これは、職場における改善・変革の能力における課題を推測させるものである。
報告書
報告書のPDFファイルは下記から閲覧・ダウンロードできます。
【 章別 】
・第1章 組織風土の全体像
(1) 組織風土とは何か
(2) 働く人にとっての組織風土
・第2章 個人と組織(職場)との関係
(1) 組織風土のとらえ方の個人差
(2) 組織(職場)が個人の意識や感情に与える影響
(3) 組織(職場)がやめるべきもの
・第3章 個人と組織との距離感
(1) 個人と組織との距離感の実態
(2) 職場との距離の取り方
【 全体版 】
組織風土研究会 報告書 (全文)

